上原です。
このブログで地味に好評な「マネーの虎に学ぶビジネス学講座」ですが、今回ははこちらの
「高級ハンドメイド家具店開業編」
について考察してみます。
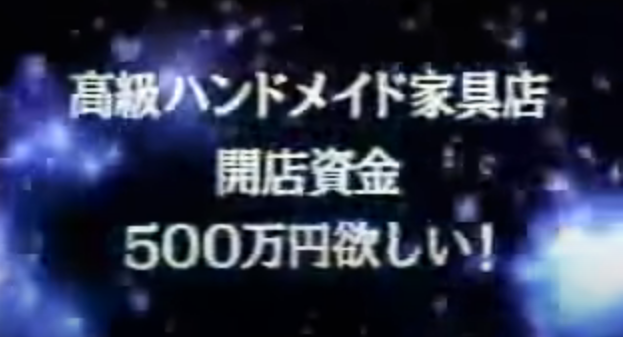
プレゼンターは26歳の家具職人、菊野慶吾さん。
やりたい事業は「高級ハンドメイド家具店の開業」とのこと。
希望した金額は500万円でした。
志願者の菊野慶吾さんは既に個人でハンドメイド家具の販売を行っているようで、父親の代から続く「店舗」兼「工場」で販売を行っているものの、 その店舗を「カフェ」のようなスタイルにして、 自分のハンドメイド家具をそこに並べ、
「カフェスタイルのハンドメイド家具の販売店をやりたい」
というビジネスプランを持っていました。
希望額500万円はその「カフェスタイルのお店」を開業する為の言わば、内装費、工事費などであると推察出来ます。
ちなみにこの当時26才家具職人の菊野慶吾さんですが、マネーの虎で実際に500万円を手にしてお店を改装し、カントリーウッドガーデンという会社を設立して、今はインターネット通販を中心に家具の販売を行っているようです。
業績の程は分かりませんが、情報を調べる限りでは、このマネーの虎の放送からあの手この手で、色々と事業を展開していた事が伺えますので、実はそれなりにやり手の人物だったのかもしません。
マネーの虎の放送映像では緊張のあまり、プレゼンを途中で止めてしまったり、あまり口が上手くないところが垣間見えていたので、
「ちょっと人のよさそうな憎めない経営者」
という感じの好青年だったのですが、マネーの虎以降の彼のビジネス展開の傾向は、その印象とはいい意味でギャップがあります。
虎から金を引き出すためにあえて情に訴えるような人柄を演じていたのであれば、経営手腕に負けず劣らず大した役者ぶりです。
それはともかく、当時は世間的にまだそこまで主流ではなかったネットショップをマネーの虎の放送で知名度があるうちにすぐに始めている点や
・ミニチュア家具
・ドールハウス
といった新手の商品を手掛け、これもネット通販から、かなり売れた様子が伺えます。
要するにマネーの虎に出演した経営者の中では、かなり少数派な「今も経営を続けている経営者」の一人なわけです。
そんな当時26才の家具職人の菊野慶吾さんですが、そのプレゼンテーションの一部始終はかなりの面白展開で、マネーの虎ファンの間では神回のひとつと言われています。
最終的には3人の「虎」が全額500万円の投資で名乗りを上げ、志願者がその3人の虎の一人を選ぶという展開となったのです。
その3人の虎というのが、
・当時の生活創庫、堀之内九一郎社長
・株式会社モノリス、岩井良明社長
・当時の株式会社ラヴ、貞廣一鑑社長
この3名でした。
ただ、それぞれの社長の投資のスタンス、動機は、岩井良明社長と貞廣一鑑社長はほぼ近いものでしたが、堀之内九一郎社長は大きく異なるものでした。
岩井良明社長と貞廣一鑑社長の両名は、ほぼ経営等は全て志願者の自由にするという条件で、基本的には「お金だけを出す」という投資スタンス。
投資の動機は、単純に志願者の人柄に惹かれ、実際の商品などを目にした上で、家具職人としての腕も間違いなさそうと判断したのでしょう。
この2人の投資の動機はいつもこのような感じなので、まあ、いつもの判断基準だったような気がします。
ただ、貞廣一鑑社長は、この家具職人の家具を
「その家具から人柄が出ている。」
「その家具そのものが菊名(志願者)さんに見える」
と、職人さん冥利に尽きる言葉を与えていました。
対して生活創庫、堀之内九一郎社長は、逆にその家具職人さんの作った家具を
「そんなものは幾らでも作れる。」
「同じような家具はどこにでもある。」
と手厳しい一蹴(笑)
ただ、家具の原価率(材料費)を聞いた上で、
「これは商売になる。」
と判断したようで、自分が手掛ける全国の店舗で、その家具を売っていく事を前提として、
「経営方針全般に口を出していいなら、投資する」
という条件を付けていました。
要するに生活創庫、堀之内九一郎社長は原価を安く作れるその家具を自分の店で販売し、その販売益を得る事を目的に「投資をする」と言ったわけです。
まあ、この時点ではそれ以上の細かい条件は出ていませんでしたが、生活創庫、堀之内九一郎社長は、
「結局、いかに安く作ってたくさん売るかが全てだ。」
という事も言っていたので、堀之内九一郎社長にお金を出してもらった場合は、
“とにかく安く、それなりの家具を大量生産しろ”
と、家具の大量生産を強いられる可能性がありました。
勿論、それで家具はたくさん仕入れてもらえるかもしれませんし、全国のお店で自分が作った家具がどんどん売れるかもしれません。
ですが自分が作りたい家具や拘りの家具は作れなくなる可能性が高く、
「ひたすら堀之内社長に言われるがままの家具を作り、それを大量に生産して卸していくだけの専属家具業者」
にされる可能性は非常に高い事が目に見えていたのです。
むしろ、そのような状況が目に見えた為、株式会社モノリスの岩井良明社長はその家具職人さんを気付かって、暗にそのようになってしまう事を指摘した上で、
「それなら自分は、お金だけ出すから経営は好きにやりな。」
と、新たな投資提案を促したような流れでした。
対して、貞廣一鑑社長は
「出来れば堀之内社長と一緒に投資をしたい」
という事を主張していた事から、堀之内九一郎社長の「販路」については、この志願者にとってはプラスになると考えた事が伺えます。
(ただ、この提案は堀之内社長がキッパリ却下しています。)
こうした条件が出揃い、この放送回では菊野慶吾さんが3人の社長のうち、一人を選ぶという非常に珍しい展開になったわけです。
その現状を踏まえて、3名の社長の提案のうち1つを選ばなければならない状況に至った訳です。
さて、あなたならどうしますか?
1億の借金を抱える「職人」である自分。
自分の好きなように経営をしてもいいという投資家と、経営は自由にさせないが商品は幾らでも売ってやるという投資家。
また、一方は自分の作る商品をきちんと評価してくれていて、もう片方はむしろ酷評で原価率という数字だけを見ている状況。
これは人生における選択としても、職人としの選択としても、ビジネスとしての選択としても難しい選択だったと思います。
志願者の結論は・・・商品を評価してくれた貞廣社長でした。
そして、実際に彼はカフェスタイルの家具店をオープンさせ、今現在については先ほど簡単に解説した通り、順風満帆な経営を続ける事が出来ている状況にあります。
結果論を言えば、彼は貞廣社長を選んでよかったのかもしれません。
ただ、私は「自分が何に重きを置くのか」によっては、堀之内九一郎社長を選んでも良かったのではないかと思います。
とにかく借金を1日でも早く完済してしまい、1円でも多くのお金を稼ぐというのであれば、堀之内九一郎社長という選択肢もアリだったと思うわけです。
まあ、当の堀之内社長はその後、経営難に陥り店舗の大半が閉店となっていますので、そこも含めた結果論を言うと、
「堀之内九一郎社長を選ばなくて良かった」
という結論に至りますが、その結果論を抜きに考えるのであれば、
「確実な仕入れと販路を提供してくれる」
という話は、モノを作り、売りたい人間にとっては決して悪い話ではありません。
勿論、堀之内社長を選ぶ場合は、
・幾らで家具を仕入れてくれるのか
・どれくらいの数をどういう条件で仕入れてくれるのか
などなど、色々と条件を煮詰める必要はあると思いますが
「カフェスタイルのハンドメイド家具店をやろう」
と思った動機が、ただ単純に、
「そうすれば家具がたくさん売れて儲かりそうだから」
というものだったのであれば、とくにその形に拘る必要はありませんし、むしろ堀之内社長の販路が確実なものになるなら、その「リスク」を取る必要さえなくなります。
ただ単純に堀之内社長のところに、家具を卸していくという作業をすれば儲かるわけですから。
ただ、自分がそのカフェスタイルの家具を「やる事」 自体に大きな意味があったなら、堀之内社長の投資提案は確かに論外だったと思います。
それこそ、そういうお店をやって実際に自分の家具に触れて本当に欲しいと思った人にだけ、そこで家具を買ってもらうような商売をしたい。
そこで拘りの家具を思う存分作りたい。
そういう思いが強いのであれば、やはり経営は自由にやらせてくれるという、岩井社長、貞廣社長が最善の選択になると思います。
ただ、この時の志願者が、
「どっちだったのか」
は、正直わかりませんし、映像を見る限りでも、家具に拘りはあるようですが、借金という現実もあり、
「とにかく家具を売って儲けたい」
という思いも強くあったように思います。
その中で、どちらかというと「感情」で、堀之内社長ではなく貞廣社長を選んだ・・・
私は何となくそういうように見えました。
ただ、これは「経営者の選択」としては、あまり良い選択の仕方ではなかったと思います。
そういう場面では「感情」を殺して、自分の「理想」を取るべきだと思うからです。
感情を殺して「利」を取る必要はありませんが、「理想」を追求できるなら「感情」など殺すべきです。
ただ、この時の志願者はあまりそこを考えず、やや「感情」だけで選択をしたように思えたという話です。
とは言え、ビジネスも人生も結果が全てですからね。
堀之内社長の「その後」を現実として見るなら、この志願者の選択は正解だったというのが結果論です。
「自分だったら、どうするか」
そう自問自答しながら見ると、この「高級ハンドメイド家具店開業編」のマネーの虎は非常に楽しめる放送回だと思います。
以上、
「マネーの虎に学ぶビジネス学講座、高級ハンドメイド家具店開業編」
の考察でした。
他の放送回における考察も行っていますので、興味があればどうぞ。
>>マネーの虎に学ぶビジネス学講座一覧
それでは上原でした。
このブログで地味に好評な「マネーの虎に学ぶビジネス学講座」ですが、今回ははこちらの
「高級ハンドメイド家具店開業編」
について考察してみます。
マネーの虎、家具職人の高級ハンドメイド家具店の開業の考察
プレゼンターは26歳の家具職人、菊野慶吾さん。
やりたい事業は「高級ハンドメイド家具店の開業」とのこと。
希望した金額は500万円でした。
志願者の菊野慶吾さんは既に個人でハンドメイド家具の販売を行っているようで、父親の代から続く「店舗」兼「工場」で販売を行っているものの、 その店舗を「カフェ」のようなスタイルにして、 自分のハンドメイド家具をそこに並べ、
「カフェスタイルのハンドメイド家具の販売店をやりたい」
というビジネスプランを持っていました。
希望額500万円はその「カフェスタイルのお店」を開業する為の言わば、内装費、工事費などであると推察出来ます。
ちなみにこの当時26才家具職人の菊野慶吾さんですが、マネーの虎で実際に500万円を手にしてお店を改装し、カントリーウッドガーデンという会社を設立して、今はインターネット通販を中心に家具の販売を行っているようです。
業績の程は分かりませんが、情報を調べる限りでは、このマネーの虎の放送からあの手この手で、色々と事業を展開していた事が伺えますので、実はそれなりにやり手の人物だったのかもしません。
マネーの虎の放送映像では緊張のあまり、プレゼンを途中で止めてしまったり、あまり口が上手くないところが垣間見えていたので、
「ちょっと人のよさそうな憎めない経営者」
という感じの好青年だったのですが、マネーの虎以降の彼のビジネス展開の傾向は、その印象とはいい意味でギャップがあります。
虎から金を引き出すためにあえて情に訴えるような人柄を演じていたのであれば、経営手腕に負けず劣らず大した役者ぶりです。
それはともかく、当時は世間的にまだそこまで主流ではなかったネットショップをマネーの虎の放送で知名度があるうちにすぐに始めている点や
・ミニチュア家具
・ドールハウス
といった新手の商品を手掛け、これもネット通販から、かなり売れた様子が伺えます。
要するにマネーの虎に出演した経営者の中では、かなり少数派な「今も経営を続けている経営者」の一人なわけです。
そんな当時26才の家具職人の菊野慶吾さんですが、そのプレゼンテーションの一部始終はかなりの面白展開で、マネーの虎ファンの間では神回のひとつと言われています。
最終的には3人の「虎」が全額500万円の投資で名乗りを上げ、志願者がその3人の虎の一人を選ぶという展開となったのです。
その3人の虎というのが、
・当時の生活創庫、堀之内九一郎社長
・株式会社モノリス、岩井良明社長
・当時の株式会社ラヴ、貞廣一鑑社長
この3名でした。
ただ、それぞれの社長の投資のスタンス、動機は、岩井良明社長と貞廣一鑑社長はほぼ近いものでしたが、堀之内九一郎社長は大きく異なるものでした。
岩井良明社長と貞廣一鑑社長の両名は、ほぼ経営等は全て志願者の自由にするという条件で、基本的には「お金だけを出す」という投資スタンス。
投資の動機は、単純に志願者の人柄に惹かれ、実際の商品などを目にした上で、家具職人としての腕も間違いなさそうと判断したのでしょう。
この2人の投資の動機はいつもこのような感じなので、まあ、いつもの判断基準だったような気がします。
ただ、貞廣一鑑社長は、この家具職人の家具を
「その家具から人柄が出ている。」
「その家具そのものが菊名(志願者)さんに見える」
と、職人さん冥利に尽きる言葉を与えていました。
対して生活創庫、堀之内九一郎社長は、逆にその家具職人さんの作った家具を
「そんなものは幾らでも作れる。」
「同じような家具はどこにでもある。」
と手厳しい一蹴(笑)
ただ、家具の原価率(材料費)を聞いた上で、
「これは商売になる。」
と判断したようで、自分が手掛ける全国の店舗で、その家具を売っていく事を前提として、
「経営方針全般に口を出していいなら、投資する」
という条件を付けていました。
要するに生活創庫、堀之内九一郎社長は原価を安く作れるその家具を自分の店で販売し、その販売益を得る事を目的に「投資をする」と言ったわけです。
まあ、この時点ではそれ以上の細かい条件は出ていませんでしたが、生活創庫、堀之内九一郎社長は、
「結局、いかに安く作ってたくさん売るかが全てだ。」
という事も言っていたので、堀之内九一郎社長にお金を出してもらった場合は、
“とにかく安く、それなりの家具を大量生産しろ”
と、家具の大量生産を強いられる可能性がありました。
勿論、それで家具はたくさん仕入れてもらえるかもしれませんし、全国のお店で自分が作った家具がどんどん売れるかもしれません。
ですが自分が作りたい家具や拘りの家具は作れなくなる可能性が高く、
「ひたすら堀之内社長に言われるがままの家具を作り、それを大量に生産して卸していくだけの専属家具業者」
にされる可能性は非常に高い事が目に見えていたのです。
むしろ、そのような状況が目に見えた為、株式会社モノリスの岩井良明社長はその家具職人さんを気付かって、暗にそのようになってしまう事を指摘した上で、
「それなら自分は、お金だけ出すから経営は好きにやりな。」
と、新たな投資提案を促したような流れでした。
対して、貞廣一鑑社長は
「出来れば堀之内社長と一緒に投資をしたい」
という事を主張していた事から、堀之内九一郎社長の「販路」については、この志願者にとってはプラスになると考えた事が伺えます。
(ただ、この提案は堀之内社長がキッパリ却下しています。)
こうした条件が出揃い、この放送回では菊野慶吾さんが3人の社長のうち、一人を選ぶという非常に珍しい展開になったわけです。
堀之内社長か、岩井社長か、貞廣社長か。家具職人の運命の選択
ただ、この時この志願者には父親が残した 総額1億円という借金があったそうで、それを肩代わりして支払いたいという事情もありました。その現状を踏まえて、3名の社長の提案のうち1つを選ばなければならない状況に至った訳です。
さて、あなたならどうしますか?
1億の借金を抱える「職人」である自分。
自分の好きなように経営をしてもいいという投資家と、経営は自由にさせないが商品は幾らでも売ってやるという投資家。
また、一方は自分の作る商品をきちんと評価してくれていて、もう片方はむしろ酷評で原価率という数字だけを見ている状況。
これは人生における選択としても、職人としの選択としても、ビジネスとしての選択としても難しい選択だったと思います。
志願者の結論は・・・商品を評価してくれた貞廣社長でした。
そして、実際に彼はカフェスタイルの家具店をオープンさせ、今現在については先ほど簡単に解説した通り、順風満帆な経営を続ける事が出来ている状況にあります。
結果論を言えば、彼は貞廣社長を選んでよかったのかもしれません。
ただ、私は「自分が何に重きを置くのか」によっては、堀之内九一郎社長を選んでも良かったのではないかと思います。
とにかく借金を1日でも早く完済してしまい、1円でも多くのお金を稼ぐというのであれば、堀之内九一郎社長という選択肢もアリだったと思うわけです。
まあ、当の堀之内社長はその後、経営難に陥り店舗の大半が閉店となっていますので、そこも含めた結果論を言うと、
「堀之内九一郎社長を選ばなくて良かった」
という結論に至りますが、その結果論を抜きに考えるのであれば、
「確実な仕入れと販路を提供してくれる」
という話は、モノを作り、売りたい人間にとっては決して悪い話ではありません。
勿論、堀之内社長を選ぶ場合は、
・幾らで家具を仕入れてくれるのか
・どれくらいの数をどういう条件で仕入れてくれるのか
などなど、色々と条件を煮詰める必要はあると思いますが
「カフェスタイルのハンドメイド家具店をやろう」
と思った動機が、ただ単純に、
「そうすれば家具がたくさん売れて儲かりそうだから」
というものだったのであれば、とくにその形に拘る必要はありませんし、むしろ堀之内社長の販路が確実なものになるなら、その「リスク」を取る必要さえなくなります。
ただ単純に堀之内社長のところに、家具を卸していくという作業をすれば儲かるわけですから。
ただ、自分がそのカフェスタイルの家具を「やる事」 自体に大きな意味があったなら、堀之内社長の投資提案は確かに論外だったと思います。
それこそ、そういうお店をやって実際に自分の家具に触れて本当に欲しいと思った人にだけ、そこで家具を買ってもらうような商売をしたい。
そこで拘りの家具を思う存分作りたい。
そういう思いが強いのであれば、やはり経営は自由にやらせてくれるという、岩井社長、貞廣社長が最善の選択になると思います。
ただ、この時の志願者が、
「どっちだったのか」
は、正直わかりませんし、映像を見る限りでも、家具に拘りはあるようですが、借金という現実もあり、
「とにかく家具を売って儲けたい」
という思いも強くあったように思います。
その中で、どちらかというと「感情」で、堀之内社長ではなく貞廣社長を選んだ・・・
私は何となくそういうように見えました。
ただ、これは「経営者の選択」としては、あまり良い選択の仕方ではなかったと思います。
そういう場面では「感情」を殺して、自分の「理想」を取るべきだと思うからです。
感情を殺して「利」を取る必要はありませんが、「理想」を追求できるなら「感情」など殺すべきです。
ただ、この時の志願者はあまりそこを考えず、やや「感情」だけで選択をしたように思えたという話です。
とは言え、ビジネスも人生も結果が全てですからね。
堀之内社長の「その後」を現実として見るなら、この志願者の選択は正解だったというのが結果論です。
「自分だったら、どうするか」
そう自問自答しながら見ると、この「高級ハンドメイド家具店開業編」のマネーの虎は非常に楽しめる放送回だと思います。
以上、
「マネーの虎に学ぶビジネス学講座、高級ハンドメイド家具店開業編」
の考察でした。
他の放送回における考察も行っていますので、興味があればどうぞ。
>>マネーの虎に学ぶビジネス学講座一覧
それでは上原でした。
PR
マネーの虎、立花洋さんの世界一のパスタ屋の考察
上原です。
マネーの虎に学ぶビジネス学講座ということで、今回は立花洋さんという人の「世界一のパスタ屋編」を考察してみます。
マネーの虎に学ぶビジネス学講座ということで、今回は立花洋さんという人の「世界一のパスタ屋編」を考察してみます。
マネーの虎、世界一のパスタ屋。考察
プレゼンターは44歳、無職の男性で、やりたい事業は「イタリアンレストランチェーンの開業」とのこと。
希望した金額は980万円でした。
先に結論を言うと、この回はマネーが成立した回で、出資を受けた男性は現在4店舗まで店舗数を拡大しています。
2014年頃の情報で年商が2億2000万円。
4店舗で従業員50名という事ですので、この規模で年商2億であれば経営者(オーナー)さんにそこまで大きな収入は無いと思いますが、世間一般的には普通に「成功例」の1つに挙げられるのではないかと思います。
2億円の売り上げに対して材料費を30%ほどに見積もると
材料費:2億×60%=6000万円
従業員、一人あたりの平均給与が1カ月20万円だとして
50名の人件費:1000万×12カ月=1億2000万円
4店舗のテナント賃料が平均50万円ほどだとして、
テナント賃料:50万×4店舗×12カ月=2400万円
かなり乱暴な計算ですが、これで諸経費が2億400万円なので、年商2億2000万円との差し引きは1600万円。
税金を差し引いてオーナーさんの手元には毎月80万円ちょっと残っている位でしょうかね。
これを成功していると捉えるかは人それぞれですが、個人的には
「飲食店の経営者としては成功している」
と言って良いラインだと思います。
ただ、この「世界一のパスタ屋」を提唱した立花洋さん(当時44才、無職)に出資をしたのは、飲食店経営とは全く無縁のだった加藤和也社長でした。
美空ひばりさんの息子さんとして出演していた、ひばりプロダクションの社長さんですね。
一方で、その志願者である立花洋さんのプランを
「儲からない」
「利益が出ない」
と真っ向から完全否定したのが、当時は飲食店経営で成功を納めたいた安田久社長でした。
ただ、実際にはこの立花洋さんのイタリアンレストランは現在4店舗に店舗数を拡大する成功を納め、彼のビジネスプランを「儲からない」と否定した安田久社長は、2011年頃に自身の会社を倒産させています。
そして、そんな2人(立花洋さん、安田久社長)の末路は、現にこの「マネーの虎」の放送内容における立花洋さんの考え方、ビジネスプランと、それを完全否定した安田久社長の考え方に現れているところがあります。
後に明暗を分けた立花洋さんと安田久社長の経営視点
「世界一のイタリアンレストランチェーンを開業したい。」
そう豪語した立花洋さんの経営プランは何ら奇をてらったものでも何でも無く、その方針は至ってシンプルなものでした。
簡単に言えば、
「お客様目線で最大のサービスをする」
という事。
彼自身にはそれなりの接客業経験があり、そういう人材を育てられるというのが1つの自信であり、具体的なプランとして上げていたのは、
「材料費を上げて本当においしいものを提供する。」
という事でした。
逆に言えば、彼の経営プランは本当にただ「これだけ」で、
『材料費を上げてでも本当においしいものを提供して、最高の接客をしてお客さんを満足させていけば、それで世界一のイタリアンレストランを目指せる。』
というものだったわけです。
私はイタリアンレストランの経営やコンサル経験は無いので、その材料費の比率がどれくらいのものなのかは分からないのですが、立花洋さん曰く大半のお店は20%の材料費を切るそうです。
要するに一般的なレストランだと200円で作れるパスタ、1000円で作れるピザを出している、という話です。
立花洋さんはそこを30%、40%の材料費にして、同じ値段でもっとおいしい料理を出せば、お客さんはもっと満足してお店に来てくれるだろう。
というような経営プランを提案したわけです。
そしてこのプランを全面否定したのが安田久社長です。
それじゃ儲からないし、やっていけない、と言ったわけですね。
ただ、私的にどうも腑に落ちない部分があって、なぜ安田久社長がこの経営プランを、そこまで「儲からない」と否定したのかという部分です。
それこそ当時は飲食店の経営を何店舗もやっている安田久社長なら、この経営プランがさほど問題なく「成り立つもの」である事くらいは容易に想定できたんじゃないかと思うのは私だけなんでしょうか。
何故なら、これは何もそこまで難しい計算がいる話では無いからです。
例えば「全20席のレストラン」を開業するとして、少し数字を分かり易くする為の例を簡単な数字のみにしますが、
稼動率50% 客単価2000円
この条件で材料費の原価率が20%だったなら、客単価に対しての利益は1600円になります。
とすると、そのお店の一日あたりの売り上げは
1日10組(稼働率50%):16000円
という事になります。
一方で、材料費を2倍の40%にする事で顧客満足度を上げ、その稼動率が1.5倍の75%になった場合、
原価率40%で客単価に対しての利益:1200円
という計算になりますが、稼働率が75%で、
1日15組(稼働率75%):18000円
という数字になります。
材料費を2倍にしていますから、単純に2倍おいしいものを作ってお店の稼働率(集客力)を1.5倍に上げられれば、この通り普通に儲けは後者の方が大きくなるわけです。
これが2倍の集客率になればもっと儲かる事は一目瞭然です。
ただ、実際の飲食店において「2倍おいしいものを作る事」はそれくらいの集客効果、リピーター率の向上に繋がります。
まあ、材料費を2倍にして2倍おいしいものを作れるかは、コックさんの腕前とか色々な要素が考えられますが、志願者である立花洋さんが言いたかった事、提唱したかったプランは概ねこういう考えだと思います。
数字で見ても物凄く単純な話ですよね。
ただ、実際に飲食店を複数経営していた安田久社長がこんな単純な計算を出来ないはずが無く、
「それでは儲からない(成りたたない)」
と言ったのは、立花洋さんの経営プランを、違った方向で極点に捉え過ぎていたからとしか思えません。
安田久社長曰く。
「材料費を上げるとおいしいものは作れるが利益は圧迫される」
「利益で会社、店が成りたち、従業員を食わせていける。」
「だから利益を圧迫するような経営は成り立たない。」
このような意見を述べていましたが、先程の計算の通り材料費をそれなりに上げたとしても、それ相応の顧客満足度を引き出せれば、それ以上の費用対効果を生む事は実際に可能なはずなんです。
にも関わらず真っ向から立花洋さんのプランを否定したのは、安田久社長の飲食店経営の視点とか思考の中に、
「おいしいものを作っても顧客満足度は変わらない。」
「顧客満足度を高めても稼働率、リピート率は変わらない」
というものが根本としてあったからなんじゃないかと思います。
そうでなければ、立花洋さんのプランをあそこまで真っ向否定する事は無いと思うからです。
言い方を変えると、安田久社長の経営者としての思考は、
「飲食店において料理の味はそこまで重要じゃない。」
「顧客満足度なんて、そこまで高める必要はない。」
という考えが根底にあり、突き詰めると実際に成功している自分のお店が、
「何故、うまくいっているのか」
もあまり正しくは認識していなかったんじゃないかと思います。
顧客満足度を追及しない飲食店が成功していたのですから、それはおそらく「結果として」顧客満足度を取れていたか、たまたまの「流行」に乗れていただけなのかもしれません。
事実として安田久社長は2011年に会社を潰していますしね。
なので、この当時の安田久社長は自分なりの間違った飲食店経営の成功論理を持っていて、その論理の中には、
「材料費を上げてお客さんの満足度を高める」
という視点や考え方は全く無かったのだと思います。
だからこそ、立花洋さんの経営プランに対して、
「ただ利益を圧迫させるだけ」
という意見しか出て来なかったんじゃないでしょうか。
そう豪語した立花洋さんの経営プランは何ら奇をてらったものでも何でも無く、その方針は至ってシンプルなものでした。
簡単に言えば、
「お客様目線で最大のサービスをする」
という事。
彼自身にはそれなりの接客業経験があり、そういう人材を育てられるというのが1つの自信であり、具体的なプランとして上げていたのは、
「材料費を上げて本当においしいものを提供する。」
という事でした。
逆に言えば、彼の経営プランは本当にただ「これだけ」で、
『材料費を上げてでも本当においしいものを提供して、最高の接客をしてお客さんを満足させていけば、それで世界一のイタリアンレストランを目指せる。』
というものだったわけです。
私はイタリアンレストランの経営やコンサル経験は無いので、その材料費の比率がどれくらいのものなのかは分からないのですが、立花洋さん曰く大半のお店は20%の材料費を切るそうです。
要するに一般的なレストランだと200円で作れるパスタ、1000円で作れるピザを出している、という話です。
立花洋さんはそこを30%、40%の材料費にして、同じ値段でもっとおいしい料理を出せば、お客さんはもっと満足してお店に来てくれるだろう。
というような経営プランを提案したわけです。
そしてこのプランを全面否定したのが安田久社長です。
それじゃ儲からないし、やっていけない、と言ったわけですね。
ただ、私的にどうも腑に落ちない部分があって、なぜ安田久社長がこの経営プランを、そこまで「儲からない」と否定したのかという部分です。
それこそ当時は飲食店の経営を何店舗もやっている安田久社長なら、この経営プランがさほど問題なく「成り立つもの」である事くらいは容易に想定できたんじゃないかと思うのは私だけなんでしょうか。
何故なら、これは何もそこまで難しい計算がいる話では無いからです。
例えば「全20席のレストラン」を開業するとして、少し数字を分かり易くする為の例を簡単な数字のみにしますが、
稼動率50% 客単価2000円
この条件で材料費の原価率が20%だったなら、客単価に対しての利益は1600円になります。
とすると、そのお店の一日あたりの売り上げは
1日10組(稼働率50%):16000円
という事になります。
一方で、材料費を2倍の40%にする事で顧客満足度を上げ、その稼動率が1.5倍の75%になった場合、
原価率40%で客単価に対しての利益:1200円
という計算になりますが、稼働率が75%で、
1日15組(稼働率75%):18000円
という数字になります。
材料費を2倍にしていますから、単純に2倍おいしいものを作ってお店の稼働率(集客力)を1.5倍に上げられれば、この通り普通に儲けは後者の方が大きくなるわけです。
これが2倍の集客率になればもっと儲かる事は一目瞭然です。
ただ、実際の飲食店において「2倍おいしいものを作る事」はそれくらいの集客効果、リピーター率の向上に繋がります。
まあ、材料費を2倍にして2倍おいしいものを作れるかは、コックさんの腕前とか色々な要素が考えられますが、志願者である立花洋さんが言いたかった事、提唱したかったプランは概ねこういう考えだと思います。
数字で見ても物凄く単純な話ですよね。
ただ、実際に飲食店を複数経営していた安田久社長がこんな単純な計算を出来ないはずが無く、
「それでは儲からない(成りたたない)」
と言ったのは、立花洋さんの経営プランを、違った方向で極点に捉え過ぎていたからとしか思えません。
安田久社長曰く。
「材料費を上げるとおいしいものは作れるが利益は圧迫される」
「利益で会社、店が成りたち、従業員を食わせていける。」
「だから利益を圧迫するような経営は成り立たない。」
このような意見を述べていましたが、先程の計算の通り材料費をそれなりに上げたとしても、それ相応の顧客満足度を引き出せれば、それ以上の費用対効果を生む事は実際に可能なはずなんです。
にも関わらず真っ向から立花洋さんのプランを否定したのは、安田久社長の飲食店経営の視点とか思考の中に、
「おいしいものを作っても顧客満足度は変わらない。」
「顧客満足度を高めても稼働率、リピート率は変わらない」
というものが根本としてあったからなんじゃないかと思います。
そうでなければ、立花洋さんのプランをあそこまで真っ向否定する事は無いと思うからです。
言い方を変えると、安田久社長の経営者としての思考は、
「飲食店において料理の味はそこまで重要じゃない。」
「顧客満足度なんて、そこまで高める必要はない。」
という考えが根底にあり、突き詰めると実際に成功している自分のお店が、
「何故、うまくいっているのか」
もあまり正しくは認識していなかったんじゃないかと思います。
顧客満足度を追及しない飲食店が成功していたのですから、それはおそらく「結果として」顧客満足度を取れていたか、たまたまの「流行」に乗れていただけなのかもしれません。
事実として安田久社長は2011年に会社を潰していますしね。
なので、この当時の安田久社長は自分なりの間違った飲食店経営の成功論理を持っていて、その論理の中には、
「材料費を上げてお客さんの満足度を高める」
という視点や考え方は全く無かったのだと思います。
だからこそ、立花洋さんの経営プランに対して、
「ただ利益を圧迫させるだけ」
という意見しか出て来なかったんじゃないでしょうか。
南原竜樹社長からの詰問
また、この放送回では立花洋さんの経営プランに対して、南原竜樹社長からもこのような詰問がなされています。
『世界一を目指すなら、これまでに無かった何かを教えて欲しい。こんなサービスはこれまで無かったとか、そういうものが欲しい』
この質問に対して、立花洋さんは黙り込みました。
黙り込んだ理由は南原竜樹社長が言うようなもの、そのようなサービスプランは存在しなかったからだと思います。
ただ、この質問に黙り込んだ立花洋さんの気持ちは、
「そもそも、自分が提案している経営プランは、そういう奇をてらう方針で押し進めるものじゃないんだよ!」
というものだったんじゃないかと思います。
南原竜樹社長は、世界一を目指すなら、
「これまでに無い何か新しいものが必要」
という趣旨の意見を述べ、それを立花洋さんに求めました。
ですが、立花洋さんの世界一を目指す方針は、
「そんな物珍しい何かに頼るのではなく、本心でお客さんをどこよりも満足させるお店を作れれば、そういうお店はおのずと世界一のお店になっていく」
というものであり、だからこそ、
・材料費を上げて料理をおいしくして顧客満足度を高める
・最高の接客サービスでお客さんを満足させる
というプランを掲げていたのです。
“それを徹底していく事こそが「世界一のお店作り」である”
これが立花洋さんの経営プランであり、考え方だったわけです。
要するに、その「世界一のお店を作る為に不可欠だと思うもの」が南原竜樹社長と立花洋さんとでは全く異なるものだったわけですね。
勿論、南原竜樹社長の言うような、
「これまでに無い何か」
を武器にしてこそ注目と脚光が集まり、世界一を目指せるお店が作れるというのも1つの考え方です。
ただ、私はどちらかと言うと立花洋さんのような「王道を突き進む考え方」の方が好きです。
そして統計的に言うなら、そういうお店やビジネスの方が、結果的には長く成果を上げ、成功しているものだと思います。
奇をてらったものでは一時的な成功は掴めても長続きはしません。
結局、そういった「圧倒的な武器」があったとしても、最後には立花洋さんの提唱している根本的なものが不可欠になってきます。
飲食店の経営においては、
・材料費を上げて料理をおいしくして顧客満足度を高める事
・最高の接客サービスでお客さんを満足させる事
この2つこそが最も重要である事は揺るぎないと思うからです。
「おいしい」
「接客、サービスがいい」
飲食店であれば、この当たり前の事が実際に「どこよりも」出来ていれば、おのずとそのお店は成功すると思いますし、逆にそれが出来ていないとお店は何をやっても駄目だと思います。
要するに奇をてらうだけでは駄目だという事。
そんな王道を真っ直ぐ進む事しか考えない、立花洋さんの経営プランに賛同し、お金を出したのは飲食店の経営等には一切明るくない加藤和也社長だったというのはなかなか面白い結末ですよね。
ただ、飲食店の経営経験などが無いからこそ、当の加藤和也社長も「飲食店を選ぶお客さんの目線」で、立花洋さんの話を素直に聞けたんじゃないかと思います。
『彼にお店を任せればきっと成功する』
『彼の経営の考え方こそが成功するお店の考え方だ』
と、お客側の目線で直感したんだと思います。
自分が稼ぎ出した金じゃなくて親の遺産とは言え、その直感だけで980万円を出資出来る器量はさすがです。
その後も「マネーの虎」達の質問に対して、立花洋さんは多いの「自分のプラン」をアピールしていきます。
『自分の長所、ウリは何?』
→お客さんを絶対笑顔にする自信がある
『世界一を目指すなら、これまでに無かった何かを教えて欲しい。こんなサービスはこれまで無かったとか、そういうものが欲しい』
この質問に対して、立花洋さんは黙り込みました。
黙り込んだ理由は南原竜樹社長が言うようなもの、そのようなサービスプランは存在しなかったからだと思います。
ただ、この質問に黙り込んだ立花洋さんの気持ちは、
「そもそも、自分が提案している経営プランは、そういう奇をてらう方針で押し進めるものじゃないんだよ!」
というものだったんじゃないかと思います。
南原竜樹社長は、世界一を目指すなら、
「これまでに無い何か新しいものが必要」
という趣旨の意見を述べ、それを立花洋さんに求めました。
ですが、立花洋さんの世界一を目指す方針は、
「そんな物珍しい何かに頼るのではなく、本心でお客さんをどこよりも満足させるお店を作れれば、そういうお店はおのずと世界一のお店になっていく」
というものであり、だからこそ、
・材料費を上げて料理をおいしくして顧客満足度を高める
・最高の接客サービスでお客さんを満足させる
というプランを掲げていたのです。
“それを徹底していく事こそが「世界一のお店作り」である”
これが立花洋さんの経営プランであり、考え方だったわけです。
要するに、その「世界一のお店を作る為に不可欠だと思うもの」が南原竜樹社長と立花洋さんとでは全く異なるものだったわけですね。
勿論、南原竜樹社長の言うような、
「これまでに無い何か」
を武器にしてこそ注目と脚光が集まり、世界一を目指せるお店が作れるというのも1つの考え方です。
ただ、私はどちらかと言うと立花洋さんのような「王道を突き進む考え方」の方が好きです。
そして統計的に言うなら、そういうお店やビジネスの方が、結果的には長く成果を上げ、成功しているものだと思います。
奇をてらったものでは一時的な成功は掴めても長続きはしません。
結局、そういった「圧倒的な武器」があったとしても、最後には立花洋さんの提唱している根本的なものが不可欠になってきます。
飲食店の経営においては、
・材料費を上げて料理をおいしくして顧客満足度を高める事
・最高の接客サービスでお客さんを満足させる事
この2つこそが最も重要である事は揺るぎないと思うからです。
「おいしい」
「接客、サービスがいい」
飲食店であれば、この当たり前の事が実際に「どこよりも」出来ていれば、おのずとそのお店は成功すると思いますし、逆にそれが出来ていないとお店は何をやっても駄目だと思います。
要するに奇をてらうだけでは駄目だという事。
そんな王道を真っ直ぐ進む事しか考えない、立花洋さんの経営プランに賛同し、お金を出したのは飲食店の経営等には一切明るくない加藤和也社長だったというのはなかなか面白い結末ですよね。
ただ、飲食店の経営経験などが無いからこそ、当の加藤和也社長も「飲食店を選ぶお客さんの目線」で、立花洋さんの話を素直に聞けたんじゃないかと思います。
『彼にお店を任せればきっと成功する』
『彼の経営の考え方こそが成功するお店の考え方だ』
と、お客側の目線で直感したんだと思います。
自分が稼ぎ出した金じゃなくて親の遺産とは言え、その直感だけで980万円を出資出来る器量はさすがです。
その後も「マネーの虎」達の質問に対して、立花洋さんは多いの「自分のプラン」をアピールしていきます。
『自分の長所、ウリは何?』
→お客さんを絶対笑顔にする自信がある
→そういう従業員を育てる自信がある
『自分の短所、欠点は?』
『自分の短所、欠点は?』
→お客さんに怠慢な態度を取った従業員に対して怒りが爆発する
『経営者として大事な事は?』
『経営者として大事な事は?』
→「お客さんの笑顔です。」
最後まで「お客さんの満足度を上げる」という方針に対して、一貫して自分自身の短所、長所、考え方をアピールしていった立花洋さん。
その多くの回答は「投資をするか否か」を判断する、ほぼ全ての社長さん等にとっては、あまり「前のめり」になるような回答では無かったと思います。
ですが、その中で彼の姿勢、人間性、経営方針を評価したのが、美空ひばりさんの息子である加藤和也社長だったわけですね。
「出してもいいな、この人だったら。」
加藤和也社長が980万円全額を出資し、マネーは成立。
立花洋さんの現在は冒頭でお伝えした通りです。
このマネーの虎「世界一のパスタ屋」編は、飲食店の経営に携わっている経営者の人にとっては、立花洋さん、安田久社長の顛末も含めて、色々と飲食店経営の本質を見つめ直せる内容だと思います。
以上、
「マネーの虎に学ぶビジネス学講座、世界一のパスタ屋編」
の考察でした。
他の放送回における考察も行っていますので、興味があればどうぞ。
>>マネーの虎に学ぶビジネス学講座一覧
参考にされてください。
それでは。
最後まで「お客さんの満足度を上げる」という方針に対して、一貫して自分自身の短所、長所、考え方をアピールしていった立花洋さん。
その多くの回答は「投資をするか否か」を判断する、ほぼ全ての社長さん等にとっては、あまり「前のめり」になるような回答では無かったと思います。
ですが、その中で彼の姿勢、人間性、経営方針を評価したのが、美空ひばりさんの息子である加藤和也社長だったわけですね。
「出してもいいな、この人だったら。」
加藤和也社長が980万円全額を出資し、マネーは成立。
立花洋さんの現在は冒頭でお伝えした通りです。
このマネーの虎「世界一のパスタ屋」編は、飲食店の経営に携わっている経営者の人にとっては、立花洋さん、安田久社長の顛末も含めて、色々と飲食店経営の本質を見つめ直せる内容だと思います。
以上、
「マネーの虎に学ぶビジネス学講座、世界一のパスタ屋編」
の考察でした。
他の放送回における考察も行っていますので、興味があればどうぞ。
>>マネーの虎に学ぶビジネス学講座一覧
参考にされてください。
それでは。
マネーの虎で1億円を希望した中華ファーストフード店の考察
上原です。
マネーの虎に学ぶビジネス学講座ということで、今回は「中華ファストフード編」を考察してみます。
マネーの虎に学ぶビジネス学講座ということで、今回は「中華ファストフード編」を考察してみます。
マネーの虎、中華ファーストフードの考察
プレゼンターは23歳の大学生で、やりたい事業は「中華のファーストフード」だそうで。

希望した金額は1億円でした。
結論から言えば・・・まあ1億という金額ですので、額も額だったというのも含め、当然のごとく「ノーマネーでフィニッシュ」だったこの回ですが、流石にこれは、あまりにも志願者のレベルが低すぎました。
23歳という年齢のわりにはとにかく全てが「甘い」の一言。
現役の大学生らしいので、社会経験もゼロ。
全てにおいて「駄目だらけ」のプレゼンでしたが、強いて駄目だったポイントを集約するなら以下の2つだと思います。
・事業におけるウリ、ポイントが根本的にズレている。
・力量、事業内容に見合わない資金を希望している。
まずこの志願者が提唱した中華のファーストフードというもの自体は、私個人の肌感でいえば実際に「やって成り立たない商売ではない」と思います。
故に、そのアイデア自体がどうこうという問題ではないのですが、志願者がその中華ファーストフードのウリにしたいポイントや、その「拘り」としてプレゼンをしていたポイントが、あまりに「飲食ビジネス」としての的からズレていました。
その中華ファーストフードの概要としては、
・若者向けのファーストフードを作りたい
結論から言えば・・・まあ1億という金額ですので、額も額だったというのも含め、当然のごとく「ノーマネーでフィニッシュ」だったこの回ですが、流石にこれは、あまりにも志願者のレベルが低すぎました。
23歳という年齢のわりにはとにかく全てが「甘い」の一言。
現役の大学生らしいので、社会経験もゼロ。
全てにおいて「駄目だらけ」のプレゼンでしたが、強いて駄目だったポイントを集約するなら以下の2つだと思います。
・事業におけるウリ、ポイントが根本的にズレている。
・力量、事業内容に見合わない資金を希望している。
まずこの志願者が提唱した中華のファーストフードというもの自体は、私個人の肌感でいえば実際に「やって成り立たない商売ではない」と思います。
故に、そのアイデア自体がどうこうという問題ではないのですが、志願者がその中華ファーストフードのウリにしたいポイントや、その「拘り」としてプレゼンをしていたポイントが、あまりに「飲食ビジネス」としての的からズレていました。
その中華ファーストフードの概要としては、
・若者向けのファーストフードを作りたい
→若者をターゲットにした安く食べられる中華のファーストフード
・「おしゃれ」で「かっこいい事」がウリである
・「おしゃれ」で「かっこいい事」がウリである
→若者はおしゃれでかっこいいものに集まる(金を落とす)
・紙のコンパクトな容器で中華を食べられるようにする
・紙のコンパクトな容器で中華を食べられるようにする
→それがとにかくおしゃれでかっこいい。
・若者にかっこいいと思ってもらう為、外観にはお金をかけたい
・若者にかっこいいと思ってもらう為、外観にはお金をかけたい
→かっこよければ若者は集まる。
と言ったもので、その「箱詰めの中華」をそのまま歩きながらでも、立ってでも食べられるようにする事で、
「そういう容器でモノを食べる行為そのものがおしゃれでかっこいい」
「そういうおしゃれでかっこいいものは流行る」
というのが志願者の主張です。
まあ、それが「おしゃれ」で「かっこいい」かどうかは人それぞれのセンスや感覚によって分かれるところでしょうし、志願者自身はそれを本気で「かっこいい」と思っている点からも、その志願者と同じ感覚を持っている人はそのように思うのかもしれません。
と言ったもので、その「箱詰めの中華」をそのまま歩きながらでも、立ってでも食べられるようにする事で、
「そういう容器でモノを食べる行為そのものがおしゃれでかっこいい」
「そういうおしゃれでかっこいいものは流行る」
というのが志願者の主張です。
まあ、それが「おしゃれ」で「かっこいい」かどうかは人それぞれのセンスや感覚によって分かれるところでしょうし、志願者自身はそれを本気で「かっこいい」と思っている点からも、その志願者と同じ感覚を持っている人はそのように思うのかもしれません。
(私は全く思いませんが)
事実、そういった感覚的な部分やセンス的な部分で、自分に近い感覚を持っている人というのは、自分がよほどズレていなければ少なからずいるものです。
そして大半の人は「流行り」に流されていく傾向にありますので、それが「かっこいいんだ」という風潮になれば、実際にそれを「かっこいい」と思う人は増えていきます。
ですので、志願者の「おしゃれ」「かっこいい」という感覚や、それを形にしていこうという事自体はとくに問題ありません。
要するにそういった感覚やセンスなどによるものは、マーケティング等をどう仕掛けて「流行らせるか」で、どうにでもないポイントであるという事です。
結局、世の中の大半の人は「流行れば」それに流されていくからです。
それはほんの一昔前の「フャッション」などを見ても一目瞭然ですし、10年、20年前に今の人の達最先端のファッションがそのまま受け入れられるかと言えば、難しいはずです。
要するにそういった感覚的なセンスなどは何が正解というものがあるものでもなく、
「流行ればそれが正解になるもの」
であり、流行りはその「仕掛け方」で作り出せるものなので、私達マーケッターにとっては、そういった感覚やセンスが今現在の時点で「ある」「ない」という視点はどうでもいいわけです。
「何それ?」
としか思えないようなものでも、仕掛け方次第ではいかようにも流行らせられるものだからです。
ただ、この志願者の「センスの無さ」は、そういった「おしゃれ」「かっこいい」のセンスではなく、その「おしゃれ」「かっこいい」という感覚を
「飲食」
「ファーストフード」
にそのまま当て込んでしまったところにあると思います。
事実、そういった感覚的な部分やセンス的な部分で、自分に近い感覚を持っている人というのは、自分がよほどズレていなければ少なからずいるものです。
そして大半の人は「流行り」に流されていく傾向にありますので、それが「かっこいいんだ」という風潮になれば、実際にそれを「かっこいい」と思う人は増えていきます。
ですので、志願者の「おしゃれ」「かっこいい」という感覚や、それを形にしていこうという事自体はとくに問題ありません。
要するにそういった感覚やセンスなどによるものは、マーケティング等をどう仕掛けて「流行らせるか」で、どうにでもないポイントであるという事です。
結局、世の中の大半の人は「流行れば」それに流されていくからです。
それはほんの一昔前の「フャッション」などを見ても一目瞭然ですし、10年、20年前に今の人の達最先端のファッションがそのまま受け入れられるかと言えば、難しいはずです。
要するにそういった感覚的なセンスなどは何が正解というものがあるものでもなく、
「流行ればそれが正解になるもの」
であり、流行りはその「仕掛け方」で作り出せるものなので、私達マーケッターにとっては、そういった感覚やセンスが今現在の時点で「ある」「ない」という視点はどうでもいいわけです。
「何それ?」
としか思えないようなものでも、仕掛け方次第ではいかようにも流行らせられるものだからです。
ただ、この志願者の「センスの無さ」は、そういった「おしゃれ」「かっこいい」のセンスではなく、その「おしゃれ」「かっこいい」という感覚を
「飲食」
「ファーストフード」
にそのまま当て込んでしまったところにあると思います。
センスそのものが悪いのではなく、それを向けた方向性が悪い
多くの人(消費者)が「飲食」というものに求めるものは何か、ファーストフードというものに求めるものは何か。
その飲食というものやファーストフードというものに、消費者が「求めるもの」をこの志願者は完全に間違っているというか、そこに視点すら置く事が出来ていないのが問題ではないかと思います。
要するに「飲食」と言うものにお金を出す側の人達や「ファーストフード」というところで飲食をする人達が、「かっこよさ」や「おしゃれさ」を実際に求めているのか?
そして、その要素にお金を払うのか?
という事ですね。
・・・これに関しては明らかに「求めていない」というのが大多数の消費者の感覚であり、実状だと思います。
「飲食店」というものに対しては「おしゃれさ」や「かっこよさ」という要素を求めるニーズはあると思いますが、この志願者の主張するこの中華ファーストフードのかっこよさは、
「紙のコンパクトな容器で詰められた中華を歩きながらでも立ちながらでも食べられる」
というところにあるとして、それをこの事業の「ウリ」にしています。
勿論、その容器がかっこいいという事ではなく、
「そういう容器で食べてる姿がでおしゃれでかっこいい」
と言っているわけです。
そしてその「かっこよさ」に多くの若者がひかれるだろうと。
これは言わばその「歩き食い」や「立ち食い」のスタイルがおしゃれでかっこいいと言っているわけですが、
「飲食」
「ファーストフード」
に対して、「歩き食い」や「立ち食い」のスタイルや、そのおしゃれさ、かっこよさを求めるニーズがあるでしょうか。
そこに付加価値を感じて対価を払う人がどれだけいるでしょうか。
それが「食べやすさ」という視点ならまだしも、
「歩き食い、立ち食いをしている自分のかっこよさ」
を求めて飲食やファーストフードにお金を払う人や、
「何を食べるか」
「どこで食べるか」
を決める消費者はどう考えても少数派だと思います。
要するに、例えそれが「かっこいい」と思ったとしても、その「感覚」は飲食やファーストフードという市場ではさほど「消費」には傾かない可能性が高い・・・という事です。
何よりそこまで「人目に付く事」を前提とした「歩き食い行為」「立ち食い行為」に対して、そこまで高いベクトルを持っている人も少ないと思います。
飲食は基本は店内で、テイクアウトをしたとしても、オフィス、公園、自宅が前提ではないでしょうか。
あえて「中華を歩きながら、立ちながら食べたい」と思う人は私はどう考えても少数派だと思います。
その飲食というものやファーストフードというものに、消費者が「求めるもの」をこの志願者は完全に間違っているというか、そこに視点すら置く事が出来ていないのが問題ではないかと思います。
要するに「飲食」と言うものにお金を出す側の人達や「ファーストフード」というところで飲食をする人達が、「かっこよさ」や「おしゃれさ」を実際に求めているのか?
そして、その要素にお金を払うのか?
という事ですね。
・・・これに関しては明らかに「求めていない」というのが大多数の消費者の感覚であり、実状だと思います。
「飲食店」というものに対しては「おしゃれさ」や「かっこよさ」という要素を求めるニーズはあると思いますが、この志願者の主張するこの中華ファーストフードのかっこよさは、
「紙のコンパクトな容器で詰められた中華を歩きながらでも立ちながらでも食べられる」
というところにあるとして、それをこの事業の「ウリ」にしています。
勿論、その容器がかっこいいという事ではなく、
「そういう容器で食べてる姿がでおしゃれでかっこいい」
と言っているわけです。
そしてその「かっこよさ」に多くの若者がひかれるだろうと。
これは言わばその「歩き食い」や「立ち食い」のスタイルがおしゃれでかっこいいと言っているわけですが、
「飲食」
「ファーストフード」
に対して、「歩き食い」や「立ち食い」のスタイルや、そのおしゃれさ、かっこよさを求めるニーズがあるでしょうか。
そこに付加価値を感じて対価を払う人がどれだけいるでしょうか。
それが「食べやすさ」という視点ならまだしも、
「歩き食い、立ち食いをしている自分のかっこよさ」
を求めて飲食やファーストフードにお金を払う人や、
「何を食べるか」
「どこで食べるか」
を決める消費者はどう考えても少数派だと思います。
要するに、例えそれが「かっこいい」と思ったとしても、その「感覚」は飲食やファーストフードという市場ではさほど「消費」には傾かない可能性が高い・・・という事です。
何よりそこまで「人目に付く事」を前提とした「歩き食い行為」「立ち食い行為」に対して、そこまで高いベクトルを持っている人も少ないと思います。
飲食は基本は店内で、テイクアウトをしたとしても、オフィス、公園、自宅が前提ではないでしょうか。
あえて「中華を歩きながら、立ちながら食べたい」と思う人は私はどう考えても少数派だと思います。
(大半の人は落ち着いて座って食べたいジャンルのものだと思います)
ましてそこに「他人の目」という点を意識して、おしゃれさ、かっこよさを追及する人は更に限られます。
要するにこの志願者が提唱する中華ファーストフードビジネスは、その感覚、センスを向ける方向性そのものが消費者のニーズや感覚と完全にズレてしまっているわけです。
ましてそこに「他人の目」という点を意識して、おしゃれさ、かっこよさを追及する人は更に限られます。
要するにこの志願者が提唱する中華ファーストフードビジネスは、その感覚、センスを向ける方向性そのものが消費者のニーズや感覚と完全にズレてしまっているわけです。
志願者が提唱した「マーケティング?」らしき理論
また、この志願者は一応、この中華ファーストフードビジネスのマーケティング展開(らしきもの?)も主張していました。
まあ、本当にマーケティングと言えるほどのものでもないのですが、
「まずは外国人の多い六本木に店を出して、彼等に街中でその箱詰めの中華を食べている姿を広めて貰う」
というもので、それを見た日本人が「かっこいい」と思い、こぞって真似をし始めるだろうという思惑でした。
外国人はこういった箱詰めの中華などに抵抗がないので、すぐにでも飛びついてくれるだろうというのが彼の主張です。
もともと志願者がこの「箱詰め中華」にインスパイアされたのはL.Aへホームステイを経験している時らしく、海外(アメリカ)ではそのスタイルがスタンダードなのだとか。
よって、アメリカ人が多い六本木でこの店を出せば、まずはアメリカ人から火が付いて、それを見た日本人が自分と同じように
「かっこいい!」
とインスパイアされてこの中華ファーストフードにたちまち若者が群がっていくだろう。
というのが、この志願者が考える「マーケティング(笑)」です。
まあ、先程もお伝えした通り、かっこいいという感覚やセンスは人それぞれですし、大半の人は流行に流されるのが常なので、彼のセンスや感覚がどうというのは問題ではありません。
ですが、その「かっこいい」という風潮、その「流行」を作る為の戦略、仕掛けとして
「六本木の外人がそれで食べていれば皆がかっこいいと思うだろう」
というのはかなり考えが甘いというか、それこそ「自分だけの感覚」に頼り過ぎているところがあります。
六本木の外国人が箱詰めの中華を食べているのを目に出来る人の比率。
それを見て実際に「かっこいい」と思う人の比率。
そして実際に、
「あの外人達みたいに歩きながら中華を食べたい」
と思う人の比率は正直「たかが知れている」と思います。
せいぜい、この志願者のように、外国人への憧れを強く持っている一部の人だけでしょう。
少なくともそのレベルの「仕掛け」では、それを「かっこいい」とする風潮、流行は作れないと思いますね。
今時、そこまで六本木の外国人のやっている事を見て、素直に憧れを抱くような若者が多いとは思えません。
何より六本木で遊んでいるような若者は、少々「特殊な層の若者達」だと思うので、一般的な「大多数の若者達の趣向」とは違う気がします。
基本、風潮や流行は仕掛けによって作り出せるものですが、この志願者の主張する「仕掛け」は完全に自分の感覚だけに頼り過ぎているものなので、これではおそらく上手くはいかないだろうと思います。
まあ「1億」というお金を投じるにはリスクだけが高過ぎますね。
それこそ彼が提唱するレベルのマーケティングによって、実際にそれが「かっこいい」という風潮を作れるというなら、ひとまずは移動販売の車でも用意して、その箱詰めの中華を売り歩いてみるところから始めるべきだと思います。
それなら1000万円もかけずに事業が出来ますから。
その点で、この志願者はどう考えても「1億」というお金を
「どうせ人から出してもらうお金だから」
というレベルで軽く考えていたと思います。
実際のマネーの虎という番組で得られるお金が返済義務の無い出資(投資)という形で手に出来る資金だとしても、事業としてやるからには、それを「身銭を切る事と同じ」か、それ以上の「重いお金である」という意識は絶対的に持つべきです。
自分自身に一切の「弁済義務」が無い以上、それは「人のお金で事業をする」という事なのですから、自分の全てを犠牲にしてでも利益を上げる覚悟が無ければ、人のお金でビジネスをする資格なんて無いわけです。
それこそ株式を上場させている上場企業の経営者は少なくとも、そういう意識で事業をやっているはずです。
そういう意識で事業をやってきたからこそ、株式を上場出来るような会社を実際に経営出来ているわけです。
この志願者も自分のビジネスモデル、ビジネスプランを冷静に考えれば、どう考えてもいきなり1億もの資金を投じるだけの価値、勝算、裏付けはほぼ何も無いに等しかった事は明らかです。
故に、そのレベルの事業プランで1億を打診する時点で話になりません。
この時点で
「人の金でやれるなら、やりたい」
みたいな考えの甘さ、経営者としての責任感の無さが明るみになっています。
このレベルの事業プランなら、まずは出来る限り費用を押さえた形でやってみるべきであり、その「形」に見合った資金調達を目指すべきだったと思いますね。
というか、この志願者自身が1億の「借金」を背負うという条件なら、この事業を1億円を投じて進める覚悟があったかと言えば、私は間違いなく「無かっただろう」と思います。
そんな意識の人間にお金を出す人はまずいません。
事業プランがずさんだった事は言うまでもありませんが、この志願者がノーマネーだった一番の要因はそこだと思いますね。
結果論を言えば、ここまでずさんな事業プランに対して何の根拠もない1億円というただリスクだけの高い金額を希望してきた事。
そこにその甘さや責任感の無さの全てが出ていたと思います。
出資(投資)を募る立場で事業をするというなら、自分が身銭を切る以上の高い意識と責任感を持つべきであり、その前提で事業プランや資金繰りを練るべきだという事ですね。
「中華ファーストフード」に1億円を志願した男。
この志願者の事業、この志願者自身をあなたはどう見ましたか?
以上、
「マネーの虎に学ぶビジネス学講座、中華ファーストフードに1億円を志願した男編」
でした。
他の放送回における考察も行っていますので、興味があればどうぞ。
>>マネーの虎に学ぶビジネス学講座一覧
参考にされてください。
それでは。
まあ、本当にマーケティングと言えるほどのものでもないのですが、
「まずは外国人の多い六本木に店を出して、彼等に街中でその箱詰めの中華を食べている姿を広めて貰う」
というもので、それを見た日本人が「かっこいい」と思い、こぞって真似をし始めるだろうという思惑でした。
外国人はこういった箱詰めの中華などに抵抗がないので、すぐにでも飛びついてくれるだろうというのが彼の主張です。
もともと志願者がこの「箱詰め中華」にインスパイアされたのはL.Aへホームステイを経験している時らしく、海外(アメリカ)ではそのスタイルがスタンダードなのだとか。
よって、アメリカ人が多い六本木でこの店を出せば、まずはアメリカ人から火が付いて、それを見た日本人が自分と同じように
「かっこいい!」
とインスパイアされてこの中華ファーストフードにたちまち若者が群がっていくだろう。
というのが、この志願者が考える「マーケティング(笑)」です。
まあ、先程もお伝えした通り、かっこいいという感覚やセンスは人それぞれですし、大半の人は流行に流されるのが常なので、彼のセンスや感覚がどうというのは問題ではありません。
ですが、その「かっこいい」という風潮、その「流行」を作る為の戦略、仕掛けとして
「六本木の外人がそれで食べていれば皆がかっこいいと思うだろう」
というのはかなり考えが甘いというか、それこそ「自分だけの感覚」に頼り過ぎているところがあります。
六本木の外国人が箱詰めの中華を食べているのを目に出来る人の比率。
それを見て実際に「かっこいい」と思う人の比率。
そして実際に、
「あの外人達みたいに歩きながら中華を食べたい」
と思う人の比率は正直「たかが知れている」と思います。
せいぜい、この志願者のように、外国人への憧れを強く持っている一部の人だけでしょう。
少なくともそのレベルの「仕掛け」では、それを「かっこいい」とする風潮、流行は作れないと思いますね。
今時、そこまで六本木の外国人のやっている事を見て、素直に憧れを抱くような若者が多いとは思えません。
何より六本木で遊んでいるような若者は、少々「特殊な層の若者達」だと思うので、一般的な「大多数の若者達の趣向」とは違う気がします。
基本、風潮や流行は仕掛けによって作り出せるものですが、この志願者の主張する「仕掛け」は完全に自分の感覚だけに頼り過ぎているものなので、これではおそらく上手くはいかないだろうと思います。
まあ「1億」というお金を投じるにはリスクだけが高過ぎますね。
それこそ彼が提唱するレベルのマーケティングによって、実際にそれが「かっこいい」という風潮を作れるというなら、ひとまずは移動販売の車でも用意して、その箱詰めの中華を売り歩いてみるところから始めるべきだと思います。
それなら1000万円もかけずに事業が出来ますから。
その点で、この志願者はどう考えても「1億」というお金を
「どうせ人から出してもらうお金だから」
というレベルで軽く考えていたと思います。
実際のマネーの虎という番組で得られるお金が返済義務の無い出資(投資)という形で手に出来る資金だとしても、事業としてやるからには、それを「身銭を切る事と同じ」か、それ以上の「重いお金である」という意識は絶対的に持つべきです。
自分自身に一切の「弁済義務」が無い以上、それは「人のお金で事業をする」という事なのですから、自分の全てを犠牲にしてでも利益を上げる覚悟が無ければ、人のお金でビジネスをする資格なんて無いわけです。
それこそ株式を上場させている上場企業の経営者は少なくとも、そういう意識で事業をやっているはずです。
そういう意識で事業をやってきたからこそ、株式を上場出来るような会社を実際に経営出来ているわけです。
この志願者も自分のビジネスモデル、ビジネスプランを冷静に考えれば、どう考えてもいきなり1億もの資金を投じるだけの価値、勝算、裏付けはほぼ何も無いに等しかった事は明らかです。
故に、そのレベルの事業プランで1億を打診する時点で話になりません。
この時点で
「人の金でやれるなら、やりたい」
みたいな考えの甘さ、経営者としての責任感の無さが明るみになっています。
このレベルの事業プランなら、まずは出来る限り費用を押さえた形でやってみるべきであり、その「形」に見合った資金調達を目指すべきだったと思いますね。
というか、この志願者自身が1億の「借金」を背負うという条件なら、この事業を1億円を投じて進める覚悟があったかと言えば、私は間違いなく「無かっただろう」と思います。
そんな意識の人間にお金を出す人はまずいません。
事業プランがずさんだった事は言うまでもありませんが、この志願者がノーマネーだった一番の要因はそこだと思いますね。
結果論を言えば、ここまでずさんな事業プランに対して何の根拠もない1億円というただリスクだけの高い金額を希望してきた事。
そこにその甘さや責任感の無さの全てが出ていたと思います。
出資(投資)を募る立場で事業をするというなら、自分が身銭を切る以上の高い意識と責任感を持つべきであり、その前提で事業プランや資金繰りを練るべきだという事ですね。
「中華ファーストフード」に1億円を志願した男。
この志願者の事業、この志願者自身をあなたはどう見ましたか?
以上、
「マネーの虎に学ぶビジネス学講座、中華ファーストフードに1億円を志願した男編」
でした。
他の放送回における考察も行っていますので、興味があればどうぞ。
>>マネーの虎に学ぶビジネス学講座一覧
参考にされてください。
それでは。
マネーの虎の成功者、虎と呼ばれた社長達の現在に学ぶビジネス学。
上原です。
私が高校生の頃なので、もう10年以上も前になりますが、日本テレビで「マネーの虎」という番組が放送されていました。
司会は俳優の吉田栄作さん。
番組構成はその当時の各業界で成功していた社長達を「マネーの虎」と呼び、そのマネーの虎(社長)達の前で、ビジネスで成功したい一般志願者が自分のビジネスプランをプレゼンテーションし、そのマネーの虎達から資金を募るというシンプルなもの。
そのマネーの虎達が志願者のプレゼンテーションを聞いて、実際にビジネス的な可能性を感じたり、その志願者を支援したいと思った場合は、志願者の希望額の全額かその一部を
・投資(出資する)
・融資(貸し付ける)
いずれかの形でお金(現金)を出すというのが基本ルールで、「投資」か「融資」かは、その志願者や、お金を出す虎(社長)の意向によってもまちまちだったようです。
番組上(放送上)では、あまりこの
「投資か融資か」
というところに焦点が置かれていなかった為、実際に「マネーの虎」と呼ばれる社長達が志願者にお金を出したケースもそれなりにありましたが、
「どういう条件でそのお金を出したのか」
という細かい資金提供の条件や契約内容については、ほぼ全ての出資事案が不透明だったものと記憶しています。
今だと私はどちらかと言うと「プレゼンする側」の立場より、お金を出す側の立場で見てしまうので、
「その事業への資金提供は投資なのか、融資なのか」
「その事業への資金提供は投資だったのか、融資だったのか」
というのがかなり重要なポイントに思うのですが、番組上(放送上)では、そこはあまり明確にはなってませんでした。
私が高校生の頃なので、もう10年以上も前になりますが、日本テレビで「マネーの虎」という番組が放送されていました。
司会は俳優の吉田栄作さん。
番組構成はその当時の各業界で成功していた社長達を「マネーの虎」と呼び、そのマネーの虎(社長)達の前で、ビジネスで成功したい一般志願者が自分のビジネスプランをプレゼンテーションし、そのマネーの虎達から資金を募るというシンプルなもの。
そのマネーの虎達が志願者のプレゼンテーションを聞いて、実際にビジネス的な可能性を感じたり、その志願者を支援したいと思った場合は、志願者の希望額の全額かその一部を
・投資(出資する)
・融資(貸し付ける)
いずれかの形でお金(現金)を出すというのが基本ルールで、「投資」か「融資」かは、その志願者や、お金を出す虎(社長)の意向によってもまちまちだったようです。
番組上(放送上)では、あまりこの
「投資か融資か」
というところに焦点が置かれていなかった為、実際に「マネーの虎」と呼ばれる社長達が志願者にお金を出したケースもそれなりにありましたが、
「どういう条件でそのお金を出したのか」
という細かい資金提供の条件や契約内容については、ほぼ全ての出資事案が不透明だったものと記憶しています。
今だと私はどちらかと言うと「プレゼンする側」の立場より、お金を出す側の立場で見てしまうので、
「その事業への資金提供は投資なのか、融資なのか」
「その事業への資金提供は投資だったのか、融資だったのか」
というのがかなり重要なポイントに思うのですが、番組上(放送上)では、そこはあまり明確にはなってませんでした。
(実際にお金を動かす段階では明確にしていたと思いますが)
まあ、その「融資か投資か」というところも含めて、この「マネーの虎」という番組は、その過去の放送映像をYouTubeなどで今見てもかなり面白い番組で、経営者としてはかなり勉強になるところがあります。
それこそ「お金を出す側」の社長として出演していた人達も、今はかなり明暗が分かれているような状況にあり、今も変わらず大成功している社長さんもいれば、その逆の道を辿ってしまっている社長さんも少なくありません。
そしてその番組上で「お金を出してもらう側」で出演した人も、実際にマネーの虎で資金をゲットして成功している人もいれば、番組では「ノーマネー」でも自力で成功された人もいる為、
『そんなお金を出す側、出して欲しいとお願いしていた側、双方の出演者の「今」を知った上で見る事が出来る』
というのは、リアルタイムに放送されていた頃には無い色々な視点での楽しみ方が出来るわけです。
「この社長はこんな事言ってるから後々、失敗したんだな。」
「やっぱりこの社長のこの言葉は正しかったんだな。」
というような視点で、ある意味「答え合わせ」をしながら番組を見ていく事が出来るわけですね。
まあ、その「融資か投資か」というところも含めて、この「マネーの虎」という番組は、その過去の放送映像をYouTubeなどで今見てもかなり面白い番組で、経営者としてはかなり勉強になるところがあります。
それこそ「お金を出す側」の社長として出演していた人達も、今はかなり明暗が分かれているような状況にあり、今も変わらず大成功している社長さんもいれば、その逆の道を辿ってしまっている社長さんも少なくありません。
そしてその番組上で「お金を出してもらう側」で出演した人も、実際にマネーの虎で資金をゲットして成功している人もいれば、番組では「ノーマネー」でも自力で成功された人もいる為、
『そんなお金を出す側、出して欲しいとお願いしていた側、双方の出演者の「今」を知った上で見る事が出来る』
というのは、リアルタイムに放送されていた頃には無い色々な視点での楽しみ方が出来るわけです。
「この社長はこんな事言ってるから後々、失敗したんだな。」
「やっぱりこの社長のこの言葉は正しかったんだな。」
というような視点で、ある意味「答え合わせ」をしながら番組を見ていく事が出来るわけですね。
そんな「マネーの虎」に学ぶビジネス学
そういった
「今だからこその答え合わせ」
的な見方が出来るというところも含めて、この番組はそれ以外でも経営者やビジネスマンとしては、本当に多くの事を学べる番組構成になっています。
「その事業モデルをその社長達がどう評価するか」
などの、この番組の醍醐味的なポイントはもちろん、例えば自分の事業モデルをプレゼンする側の出演者を見ても、
「そのプレゼンテーションのどこが良かったか」
「逆に何が悪かったのか」
と言った、そのプレゼンテーションの良し悪しなども、それを客観的に見ていく事で勉強になる事がかなりあります。
「その事業であれば、ここはアピールした方が良かったんじゃないか。」
「この事業なら、こういうプレゼンをするべきだったんじゃないか。」
こういった客観的な見方も出来るわけですね。
また、マネーの虎では実際に資金提供を得た出演者が、その後の事業を進めていく経過も取り上げている事があり、
「その事業がうまくいく過程」
を見ていく事も出来れば、
「その事業が失敗していく過程」
を見ていく事も出来る為、その失敗例と成功例のどちらを見ても 参考になる事、勉強になる事は非常に多いです。
それこそ、その事業のどこを改善すれば、失敗せず、成功させる事が出来た可能性が高いか等、実際に自分がコンサルをしている事業に近い業種であれば、その仮想シュミレーションが役立つ事も無いわけではありません。
そういう私の経験則も踏まえまして、この「マネーの虎」は今もかなり過去の放送映像がYouTubeなどに投稿されている状況にありますので、
「そこから実際に学び取れるビジネス学」
などを、今後私なりの視点で私見を述べていこうかと思います。
私自身が実際に勉強になったポイント等も併せてお伝えしていきますので、業種を問わず、経営者層の人や自立願望がある人には、おそらくそれなりに役立つ講座、参考になる講座になると思います。
近々、いずれかの放送分の映像を取り上げて進めてみたいと思いますので、興味があれば是非ともお付き合いください。
本日は、これからそういう講座もやってみるつもりです、、、という、ちょっとした告知とその趣旨を簡単にお伝えするご報告でした。
もし、「マネーの虎」を見た事が無ければ、YouTubeで「マネーの虎」と検索してご覧になってみてください。
たぶん、ハマると思いますよ(笑)
それでは。
- ホーム
- »
- マネーの虎のビジネス学
